![]()
 |
水本邦彦(みずもと くにひこ) 1946年、群馬県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。愛媛大学法文学部講師、助教授を経て現在、京都府立大学文学部教授。主に日本近世史を研究、社会の形成を地理的景観や自然などさまざまな角度から研究。 [主要著書] 『近世の村社会と国家』(東京大学出版会、1987年) 『近世の郷村自治と行政』(東京大学出版会、1993年) 『絵図と景観の近世』(校倉書房、2002年) 『街道の日本史 32 京都と京街道』(編著、吉川弘文館、2002年) 『草山の語る近世』(山川出版社、2003年) 『全集 日本の歴史 10 徳川の国家デザイン』(小学館、2008年) |
 |
近江学研究所紀要 近江学 創刊号 成安造形大学附属近江学研究所 発行 サンライズ出版 発売 ■A4変形並製本 ■総80頁 ■定価1890円(税込) ■書店にて発売中 木村至宏(成安造形大学学長・近江学研究所所長)「近江学概論―湖と道と山」をはじめ、福永俊彦「大津絵の誕生と三井寺別所の宗教文化圏」、水本邦彦 「近世近江の宿場町と街道―『まなざし』の視点から」など、“近江”という地域が持つ固有の風土を改めて探った学内外の研究員による論考と対談、写真家今 森光彦氏・寿福滋氏らの作品をオールカラーで収録。 |
中世から近世への変容を語る史料たち
▽今回は、学外の研究員で、ご勤務先は京都でいらっしゃる水本先生にお話をお聞きできればと思い、うかがいました。一番外からの目線で語っていただ けるかと考えたためです。水本先生は、『近江学』創刊号への論考以外に、最近では小学館から刊行が続いているシリーズ「全集 日本の歴史」の第10巻『徳 川の国家デザイン』という本を執筆なさいました。まずは、この本のことから始めさせていただければと思います。
▼そうですか。それは予想外ですが(笑)。
▽このシリーズなら、ほとんどの書店、図書館に置いてあるはずなので、手にとって水本先生のお仕事を知っていただくには一番よいと思います。一つ前 の戦国時代を対象にした8巻『戦国の活力』には興味を持っても、徳川開幕後を扱った巻はそれほどという方もいるかもしれないのですが、この本には非常に多 くの近江の事例が書かれています。また、この本は水本先生のこれまでのご研究の総まとめとしての性格も持っているかと思います。
まず、彦根の下魚屋町(しもうおやまち)のことを書いた部分。住民の詳細な居住歴が残っていたことから、それを分析なさっています。数字はグラフ化してあってとてもわかりやすいのですが、すべて水本先生によるものと考えてよろしいのでしょうか?
▼ええ、この本の執筆時に初めてやったものです。史料の紹介は、原文書の史料集のような形で以前になされていたのですが、それを細かく整理して、具体的に分析したのは、これがおそらく初めてです。
▽もとは佐和山にあった城と城下町が、彦根山(金亀(こんき)山)に移されて、いわばニュータウンができて40年ほど経った時点での調査記録です。比較的新しい住民は借屋である割合が高いなど、本当に現代のニュータウンを見るような感じですね。
▼ええ、まったく。
▽町人となった者の出身村、さらに奥さんはどこのどういう身分から嫁いできているかも記録されていて、集計すると、多い順に犬上(いぬかみ)・坂田・愛知(えち)・浅井(あざい)郡という同心円状に広がっていきます。
▼いい史料が残っていたなと思います。全国的にみても、この時期の城下町の住民のようすがわかる史料は、ほとんどないはずです。ものすごく珍しい、よい史料ですね。
▽もう一つ、分析の結果わかったことが、周辺の農村の「長男」が移住してきているということ。日本の伝統として、「家を継ぐのは長男であった」と ずっと思っていました。ところが、江戸時代初期の彦根の下魚屋町住民は、「自分は長男で、実家には弟がいる」という人が大半だった。
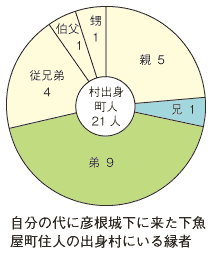
▼そうなんです。これまでの家族史の研究によると、侍の家は長男が継ぐことが多く、その風習が明治以降に農村へ広がったとされています。江戸時代で も中期・後期にはすでに農村で長男が継いでいる事例をみることができます。この彦根の史料では、きれいに「長男が家を出て行くのが普通」という結果にな り、明らかに初期の農村ではそういう傾向があったことを裏付けました。その理由ははっきりしませんが、父親と長男の年齢は近すぎ、2人の働き手はいらない から兄は先に外へ働きに出てしまい、親が老齢化した頃に下の弟が成人するようにしていたのだとする説もあります。
別の章で紹介した、坂田郡の「介若(すけわか)の後家」と呼ばれる史料に登場する地主の家も、兄の方が家を出て行ってますね。
▽あぁ、掲載されている系図では、兄の方が家を出て、石田三成と秀吉に仕え、「大坂にて切腹」とあります。
▼戦国時代から近世初期にかけての家族構成、兄弟のあり方はそれが一般的だったのでしょう。だから、兄はどんどん身分が変わっていけるわけです。町人になったり、侍になる者がいたり。
▽次に出てくるのが、甲賀(こうか)郡宇治河原(うじかわら)村(甲賀市)で、地域的な特性が出ている事例です。周囲の五つの村と河原の草刈り場や用水をめぐって喧嘩しているわけなんですが。
▼はい。「甲賀郡中惣(ぐんちゅうそう)」と呼ばれる地元の土豪たちが支配する世界があった地域で すが、彼らは織田信長に敗れ、その後、豊臣秀吉に領地を没収されます。中世的なまとまりが残っている所に、近世的ルールが入ってきて、解体しながら、変容 していくという状態です。古くからのものを継承している部分もあれば、崩れてしまった部分もある、両方が非常によくわかる地域です。
▽もとは連合体の村々の共有地と認識されていた土地が、検地後、それぞれの村単位で境界線が引かれた。そのため、弓・槍・鉄砲まで持ち出して、戦国時代さながらの紛争が起こってしまうんですね。
▼扱った史料について、これまでにも多くの研究があるのですが、それらはほとんど中世史の研究で、時代が変わったところで終わりになってしまってい たんです。史料自体はあるのに、その後の近世とのつながりがきちんと跡づけられていませんでした。戦国から、信長・秀吉・家康という時期をつなげて眺める のには非常によい事例だと思います。
▽次は、先ほど話にも出た「介若の後家」です。坂田郡箕浦(みのうら)村(米原市)に住む百姓介若の未亡人による訴訟に関する史料です。
▼これは、研究者間では非常に有名な史料です。先ほどの甲賀郡の話と同じで、戦国時代までの中世的な世界に、信長や秀吉が登場したことで、検地など の新しい政策が行われる。石高制というのは、土地の面積から納税、主従の関係まで、社会のすべてをお米の単位で数値化することです。そういう波がどっと押 し寄せたことによって、それまでの世界が崩れていく。
一方では、その新しい政策によって得をする、好条件で新たに出発できる階層=中下層の百姓たちもいる。逆に、それまで上層だった百姓は没落していきます。
▽介若家は、もともとは井戸村氏の家来だった。それが、田畑の所有権はこちらにあるといって井戸村氏側を訴えるんですね。
▼井戸村氏から耕作をまかされていた介若家は、太閤検地でも、慶長の徳川検地でも、その土地の持ち主として名前を載せてもらったのです。それを持ち 出して、「このとおり、名前が載っているじゃないか」と主張する。介若の後家にとっては、新しい政策がとられたことで、自分に有利になった。一方、それま での支配階層にとってはものすごく不利になった。そこでトラブルが生じる、そういう事例です。
▽そうやって自分の権利を守る必要があったんでしょうが、昔の日本人はよく裁判を起こしたと感じます。そして続いては、湖東地域に領地を持っていた仙台藩伊達(だて)氏と旗本の板倉氏がそれぞれ蒲生(がもう)郡内の領地に出した法度、それから同郡三津屋(みつや)村で制定された村掟の内容を紹介なさっています。
▼三つの史料とも旧八日市(ようかいち)市内のものです。かなり以前、昭和60年(1985)前後ですが、『八日市市史』の編纂をお手伝いしていた頃に史料を見る機会があって、その市史に書いたことをベースにしています。
▽幕府側の法律と、村側の掟、双方からみる形で記述されていますね。固い言葉でいえば「国家権力」と「民衆自治」の関係が考察されています。…と、ずっとこの本のことばかり、お話しているわけにもいかないので、話題を変えたいと思いますが。
▼そんなに近江のことが多いと感じられましたか(笑)、自分ではとくに意識していなかったんですが。
▽もちろん、江戸築城や島原・天草の乱など、全国的な出来事も出てきますが。この本は、県内ではぜひ郷土図書のコーナーに置いていただきたい本だと思いました(笑)。
『八日市市史』で近江の歴史に巡り会う
▽続いては、先生のお生まれまでさかのぼってお聞きしてよろしいですか。ご出身は群馬県桐生(きりゅう)市とのことで。
▼はい。生まれただけなんですけどね。
▽その後、長野県、静岡県に引っ越されて、大学進学にあたって、初めて関西の地、京都大学へ来られた。そして、研究者となられます。
▼群馬県は母親の出身地で、父親は滋賀県の旧浅井町の出身です。農学部の教員だった父の仕事の関係で、長野県の伊那谷(いなだに)に10年、小学校4年までいて、また転勤で静岡県浜松の近くに高校3年までいました。それから、大学で京都に来ました。
▽最初の論文集である『近世の村社会と国家』の「はしがき」では、「本来歴史好きでもなく」とお書きになっています。
▼(笑)そうですね。歴史が苦手だったわけではありませんが、最初、関心があったのは、方言学、国語学の方面だったんです。何度か引っ越しを繰り返 した関係もあって、言葉に興味があったのですね。同じ天竜川沿いでも上流と下流では違いますし、まして関西に来てみるとまったく違う。ですから、大学入学 当初は金田一京助のアイヌ語関係の本を読んだり、その方面をかじったりしていました。
3回生になる前に、分属といって進むコースを選択するわけですが、国文か、国史(日本史のことを当時はこう言っていました)か、どちらを選ぶかというこ とになり。当時はいわゆる「政治の時代」、学園紛争よりはもう少し前ですが、学問に対する関わり方は、個人の好みで決めるものではないという風潮もあっ て、自分の位置を知るためには歴史を学んだ方がいいのではないか、見通しがよくなるのではないか、そう思って国史を選んでしまった(笑)。とはいえ、やっ てみると、史料を読むのもおもしろくなってきて、その後ずるずると何十年かやってきたわけです。
▽最初に近江の村を題材になさったのは、『八日市市史』でよろしいのでしょうか。
▼そうです。八日市が最初です。それまでは主に摂津(大阪)や大和(奈良)の史料を使って研究していました。大学院を卒業してから、愛媛大学に5年 間勤め、それから今の京都府立大学に転勤したのですが、その頃に『八日市市史』が始まって、恩師の朝尾直弘先生から近世篇の執筆委員のお誘いをいただいた んです。八日市は史料の宝庫ですから、そこで近江の歴史に巡り会ったということになりますね。
▽昭和61年(1986)発行の『八日市市史』第3巻で、江戸時代の村の生活について執筆なさっています。
以前、ある本のための資料集めをした際に、県内の自治体史に目を通したことがあったのですが、その時に読んでいたことを思い出しました。また訴訟に関する記録なんですが…。
▼当時は実力(戦い)で解決するという世界から、奉行所に訴えて証拠調べをして解決する、あるいは、もう一度自分たちで話し合いをしてお互いに調停 しろというルールが確立した世界になっていました。そのためには、字が書けないといけないのはもちろん、訴状で自分たちが正しいということをちゃんと理屈 立てて説明しないといけない。
▽村同士の裁判のようすを詳細に、それこそ一から十まで紹介なさっています。絵師のこととか…。
▼その絵師の話はおもしろいでしょう(笑)。どっちの絵師が証拠となる絵図を描くのかで…。
▽「ひともんちゃくあった」とお書きになっています(笑)。
▼それぞれの村に都合のいい絵図を描かせるためにね。絵師を一人決めるのにさえ時間がかかる。こういうことまで記録されている史料というのもなかな かないんですよ。毎晩酒一杯飲ませるというのが条件になって京都から裁判用の絵図を描きに絵師がやってくるとかね(笑)。自分でも、おもしろがりながら紹 介した部分ですね。
思わぬ方向へ発展した土砂留役人の研究
▽初期のご研究で後々発展していくのが、「土砂留(どしゃどめ)役人(奉行)」に関するものではないかと思います。
▼淀川と大和川流域を対象に、山の土砂の流出を防ぐ、いわゆる砂防のための制度が幕府によってつくられたんです。
▽これは先生の最初期の論文の一つ(『近世の村社会と国家』に収録)ですが、おもしろいのは、もともとは「村には年に何回ぐらい侍がやって来るのか」を調べようとなさったものなんですね。今の東大阪市にあたる村に残された庄屋の日記をもとに調べると、年貢関係の検見(けみ)役人と同じぐらいの回数、「土砂留役人」が来村していたことがわかった。これは何か。全部説明すると長くなってしまいますが、近江に関わることだけいうと、膳所(ぜぜ)藩の本多(ほんだ)氏もその奉行の一人で、遠く離れた、自領ではない村々も担当していた。
▼そうです。郡単位なんです。その中に自藩の領地もあれば、他藩の領地も混ざっている。京都・大阪付近の藩領というのは、入り組んでいて郡単位です べて同一の藩というのはないんですが、面として管理しないと山の災害には対応できない。そこで、ある程度広域的な形で責任を持たせたわけです。その村の領 主ではない他藩の侍がやってきて、「ああしろ、こうしろ」と言っている。「なんだ、こいつらは?」と調べている私も思ったわけです。
▽当時の農民にとって山というのは肥料と燃料の供給源であったために、ほっておくとどんどんハゲ山だらけになってしまう。そうすると、土砂崩れが起こって大災害、下流の水害も起こりやすくなる。それを防ぐための奉行だった。
▼そこで領主側は、「植林しろ」「山に入るな」という命令をわりあい簡単に出すんですが、村の側は肥料や燃料を得るために山に入らざるをえない、そ こでいろいろな問題が起こる。近年言われるような環境保全がそう簡単にできるわけではなくて、生産活動とのせめぎ合いの中で山の問題があったことが見えて くるんです。
▽当初、政策的な面から、今でいう「広域行政」の事例として分析なさっていたものですが、さらに別の視点で発展させて、『草山の語る近世』というご著書になります。農民はなぜ、肥料を山に求めたのかというと、いわゆる金肥(きんぴ)が 広く使われるようになる以前の農法では、草が重要な肥料だったんですね。滋賀県の例でいえば、高島市のマキノスキー場ができた土地はもとは「ホトロ山」と 呼ばれる肥料にするための草山だった。昔はいたる所にそういう草山があって、緑の森林に覆われていたわけではないというお話です。
その事実自体は、水本先生のご本以前にも指摘する研究者はおられたそうですが、あまり一般的には知られていません。それはなぜですか。
▼草を肥料にするというのは、否定されていった、忘れ去られていった技術なんです。金肥が導入されると速効性もあってそれが重視され、その後は化学 肥料になります。草を使うなんて「古い」と考えられたので、農学の分野では忘れ去られていった。農学部の人に言ってもまったく知りませんし、仮に知ってい ても農学的にはほとんど関心がないわけです。一方、林学の研究者は、草なんて関心がない。ただ、戦前は牧野(ぼくや)研究といって、草地で軍馬、戦地に連れて行く馬を育てるにはどういう草がよいかという研究は非常に盛んに行われました。ところが、敗戦後はその研究もいらない。
こうして、草地、草山に関する研究はすべて忘れ去られ、誰も知らない現在があると、私は思っています。けれど、江戸時代の史料から復元してみると、今の感覚とはずいぶん違う景色の時代が長い間続いていたことがわかるわけです。
▽それこそ、稲作が始まった弥生時代からずっと続いていた農法だそうですから。
▼そうです。
▽刈った草をそのまま田んぼに踏み込む。そうすると、畔の草は刈り取られてしまい、1本もなかったということですね。村掟でも、他人の田んぼの畔の草を刈ることを禁じているぐらいで。
▼そう。今の感覚だと畔の雑草を刈り取るのは、見た目をきれいにするためぐらいに思ってしまうのだけれど、当時としては必死で、米の収穫を上げるために刈っていたんです。生業として必要だったんですね。
▽例えば、森林破壊のようにいわれるゴルフ場なども、もともと木は生えていない草山だった所も多いかもしれないですね。
▼いえ、もっと広範囲に、いわゆる里山といわれる地域の多くは草山でしたよ。機会があれば、この「近江学」の中で発表しようと思っているんですが、 江戸時代初期の湖西の山々のようすについては、わかる史料が残っています。ざっとみたところでもほとんどは、ススキやササの系統の草山です。もちろん奥山 に行けば木がありますが。私も最初は江戸時代の山争いというのは木材をめぐっての争いかと思っていたのですが、多くは草をめぐる争いだったんです。「侍が 何回来るのか」といった最初の疑問から、そんなところまで話が展開してしまったんですが(笑)。
近江の国は、道による大輪の花のイメージ
▽その他には、自治と国家権力に関するご研究などが…。
▼この調子で話していると、いつまでも「近江学」に行きませんよ(笑)。
▽では、間を飛ばして、もっとも最近の論文集として『絵図と景観の近世』という著書があります。この辺りで先生の関心の対象が変わったと考えてよろしいんでしょうか。
▼変わったというより、以前の関心対象は残したまま、新しい関心が出てきたということですね。府立大学に勤務しているということとも関わって、地域との連携や地域おこしといったことも大学の課題として必要となる中で、京都府木津(きづ)町(木津川市)や精華(せいか)町の自治体史編纂にたずさわる機会がありました。わりに村絵図がたくさん残っている地域で、それらを見る機会が増えた。
それからもう一つ、本題の「近江学」とも関連してくるのですが、平成5年(1993)から滋賀県教育委員会による「中近世古道調査」に木村至宏(よしひろ)先生のお誘いで参加することになりました。そこでも街道絵図や城下町絵図を見るようになり、絵図と景観というもう一つの筋が出てきたといえばよいかと思います。
▽中山道沿いの宿場町を描いた絵図を詳細に比較して、各宿の共通点とそれぞれの特徴などを分析なさっています。
▼これまでの古文書を中心にした研究との比較でいうと、村同士の争いなり何かの事件が起こっている現場を絵図で鳥瞰してみる、そうして広い範囲を眺 めてみると、これはここと同じことが起こっていたんだなとか、これとつながっていたんだなといったことがわかることがあります。その後で、もう一度古文書 を読んでみると、違う発見がある。よく「鳥の目、虫の目」ということが言われますが、以前の私の研究というのは地べたにいる虫の目が主体だった、それに空 からの鳥の視点を加えてみようということです。
▽今回出た『近江学』創刊号に寄稿なさっている論考も、分析の結果は非常に単純なことというか。
▼(笑)ええ、非常に単純なことです。いわれてみれば何のことはない。
▽例えば、「大津町古絵図」は、ちょうど現代の地図とは上下が逆、南が上になる描かれ方がしています。その理由は…。
▼物流の進む先である逢坂山(おうさかやま)を奥に置いた北から南への動線と、東から西端の三井寺(みいでら)へ向かう動線が札の辻で交差する形となっており、町名の上・下の付け方もその原則にのっとっていることがわかるのです。
▽それから、近江国内の道の付け方を4種類に分類なさいました。
▼行き先の地名や名勝の名前をあてた「行き先名前」、起点と終点の名前をあてた「起点終点名前」、その地の故事や由緒をあてた「固有名詞名前」、他 の道との位置関係などからついた「関係・序次・数字名前」の4つです。これらは、宿場町や村々、物流はどうなっているのか、それから道標についての今まで の研究などを調べる中で、試案としてグループ分けしたものです。
▽特に、1本の道でもどっち方向を前方と考えるかで名前が異なっていたというのは、指摘されるまでわかりませんでした。
▼これは大事なことですが、私たちは学校教育や現代の常識の中で教え込まれた特定の考え方に縛られている面があります。自分自身の感覚とは別の決ま りで、例えば地図は北を上にして描くということは世界共通のスタンダードとして守ることも大事なのですが、「どうも俺は毎日感覚的には南を見ているんだけ どな」と思う人もいるはずです。
▽あっちが、生きてる世界の正面だと。行き先名前にしても、移動手段がほぼ徒歩しか存在しなかった時代であれば、当然の感覚ですね。
▼道につけられた地名から、どこまでを射程に入れていたか、どのぐらいのエリアで暮らしが営まれていたかもわかり、当時の人のイメージが復元されると思います。
▽これまで、そういう視点からの研究はなかったんですか。
▼たぶんないと思います。「行き先名前」という言葉自体、私がつけたものですし。
▽あっ、そうなんですか。
▼勝手につけたんです(笑)。それが、近代以降、強いベクトルの名前の方に固定されていきます。例えば、最近完結した吉川弘文館の『街道の日本史』 シリーズなどに登場する街道の名前も、もともとは双方向の名前を持っていたはずですが、強い方の名前が採用されて、そちらが正式な固有名詞のようになって いるんです。
本来、伊勢へ通じる道はみんな「伊勢道」ですから、非常にたくさんの「伊勢道」がある。そして、同じ道が反対方向を進む視線では「越前道」や「敦賀道」と呼ばれる。そんなことをおもしろがって考えてみました。本当に近江は「道の国」ですから。
▽それは、お感じになりますか。
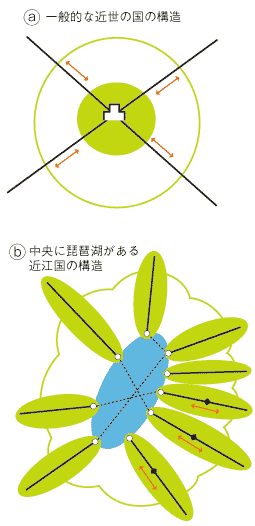
▼感じます。一つの所に集中していないんです。例えば、[右の図を書きながら](ⓐのように)お城が真ん中にある城下町で、明治以降、そこが県庁所在地に なった国の場合だと、その城下町にみんな集中してきます。幹線道路が端から端へビューッと横切って通っている構造です。こうした国はわりに多いはずです。 ところが近江は、道の代表というと東海道や中山道があがりますが、私がおもしろいと思う道は、琵琶湖から伸びて、他国へ…。
▽峠越えして。
▼そう。それらの道で一つの世界がそれぞれつくられているわけです。一方で、琵琶湖によってお互いがまたつながり合う。
▽ターミナルの役割を果たす。
▼琵琶湖の周囲にそれぞれの港がある。そこから道が他国へ向かっていく。若狭へ行く道、越前へ行く道、美濃へ行く道、伊勢へ行く道、このそれぞれで 世界ができているわけです。(ⓑのように)琵琶湖を取り巻いて、ちょうど花びらみたいに世界がいくつもあり、それが合わさったきれいな花、この全体が「近 江の国」ですよ。
一つずつの花びらは、それぞれに他の地域、他の文化と連動してる。近江八幡があって、日野があって、峠を越えて四日市へ行く。近江八幡から八日市に向かえば、八風(はっぷう)越えで桑名へ行く。これらは、みんな別の伊勢とのつながりですね。さらに水口(みなくち)・土山からは鈴鹿を経て白子へつながる。一方、今津から峠を越えれば、小浜の世界。塩津(しおつ)・海津(かいづ)から越えれば敦賀の世界。道を通じた隣の国との文化圏をつくっていたわけです。小浜や敦賀から今津、塩津へ運ばれてきた荷は、琵琶湖を通って長浜に着きます。すると、次に春照(すいじょう)(米原市)から北国脇往還で関ヶ原へ行くわけです。関ヶ原から濃州三湊と呼ばれる揖斐(いび)川の川べりに着く。そこから揖斐川の舟運で伊勢湾へ行く。大津からは都へ、また伏見経由で大阪湾、瀬戸内海とつながる。これがおもしろい。
『近江学』創刊号で木村先生が近江の文化は「湖と道と山」の三要素から構成されるとお書きになっていますが、まさにそのとおりだと思います。こういう構 造を持っているから、近江は他の国とも文化交流が盛んだったし、文化も物も集まってきた。その交流の役割を担った道はみんな「行き先名前」がついている。 逆に、伊勢の人はこの道を「近江道」と呼んでいます。伊勢からの視点は、近江のどこを指しての「近江道」なのかを知る必要がある。こういう構造だから、先 ほどの城下町を中心とした国のようには単純ではないのです。山に囲まれて近江国という一つのゆるいまとまりは形成しているけれど、花びらのように広がるこ とで、よそと連動している。
▽そういう構造だから滋賀県全体となると、一つのイメージを持つことができないのでしょうか。今でも滋賀県といえば、「琵琶湖がある所」という答えが一番多くて、何か別の統一的な性格などで表すのは難しい。
▼それは逆に、ものすごく多彩だからです。厚みがあって、広がりがある、そんな単純に何か一つの言葉で代表できるようなものではない。食べ物も、住み方も、おそらく信仰も一様ではない。同じ「なれずし」といっても、地域によってかなり違うだろうし。
自治体史は、一つひとつの花びら
▽すると、まとまりのある歴史・文化をみるためには、県内を区分した自治体史の方が適しているのかもしれません。先に『八日市市史』でのお仕事についてお話いただきましたが、現在も…。
▼『甲賀市史』や『日野町史』『秦荘(はたしょう)町史』に編集委員として関わっています。
▽そのお仕事の中では、それぞれの地域の特色が非常に出そうですか。
▼そうですね。日野が、なぜあんな所が…、「あんな所」と言ったら怒られますね。
▽いえ(笑)、正直私も訪れると、本当にそう思ってしまいます。
▼なぜ、あそこに蒲生氏が拠点を持っていたのか。じつは、あの地は琵琶湖と伊勢を結ぶ街道の拠点だったんです。ですから、江戸時代に入ってからも、仁正寺(にしょうじ)藩という藩が置かれます。水口には水口藩、それから八日市から山間に入った旧永源寺町には山上(やまがみ)藩が置かれます。ちゃんと、それぞれの街道の要所に藩が置かれる形になっていたのです(図ⓑの◆にあたる)。
▽なるほど。
▼それから、草津で中山道と分かれる東海道ですが、この道は甲賀郡の住民にとっては、地域経済の道でもありました。土山や水口では領主への年貢米の津出しを行うのにどこへ持って行くかというと、矢橋(草津市)の港へ持って行く。そこから船で大津へ。
▽そうなんですか。
▼帰りには、大津や草津で買い物をして村へ持って帰る。だから、東海道は五十三次の東海道であると同時に、地域社会の生活道路だったわけです。当時の土山・水口の人はみんな矢橋の方向を見つめていたんですよ。村の明細帳には必ず「矢橋の港」が出て来ますから。
▽あぁ、それは今の感覚とは違いますね。
▼当時、北斎や広重が見ていたのとも違う、まさに地元住民の感覚としてです。甲賀は反対方向には伊賀とも結ばれているので、伊賀への目線もある。
日野町の歴史を鳥瞰すると、安土・八幡に近い常楽寺の港から伊勢へとつながる道の中間点としての歴史がみえてくる。そういう意味では自治体史も、地域内 だけに閉じてしまわずに、他地域とのリンクの仕方を考えながら取り組むことが、その時代の地域を復元するために大事かなと思っています。
この点で、『長浜市史』に関わったことはとてもおもしろい経験でした。あそこは、日本海と伊勢湾を結ぶベルト地帯ですから。
▽明治初期までは物流の拠点として栄えた地域です。
▼『長浜市史』第7巻(地域文化財編)に執筆した「近世の地域文化財」では、長浜の絵図を、どっちの方向から描かれているかによって比較しました。 最初はお城に向かって描かれている。もう廃城になった後なのですが。それが、北国街道がメインの構図に変わって、最後には琵琶湖から伊吹山に向かう視点に 変わる。時代によって描かれ方が変わるんです。
▽伊吹山を背景にというのが、現在のイメージですね。
▼長浜も、時代によって性格を変えていった町だということが絵図によってよくわかります。その時々の特徴が絵師や注文主の目線に投影されているから です。お城を中心に描くという定番が決まっている城下町の絵図とは違う視点が出てくる近江には、やはりいろいろな花びらがある。
今後、近江学で目指すもの
▽今後、近江学の方向で考えておられるのも絵図を素材としてですか。
▼そうですね。絵図を素材に今までやってきたことを深めてもいきたいですし、先ほど話に出た里山の利用の歴史の問題、自然との関係も近江に即しても う少し調べてみたい。それから、道を例に今申し上げたような近江の文化を構成するもの、地域構造論みたいなものを、それぞれの花びら一ひら一ひらを愛でな がら考えることができたらいいなあと、そんなふうに思っています。
▽お住まいは大津市とのことですが…。
▼大津市の北部、旧志賀町にあたる所に住んでいます。
▽では、住民としてみた滋賀県の印象は。
▼府立大学に勤めるようになって、最初しばらくは京都に住んでいましたが、長く住むなら琵琶湖が見える所に住みたいなと思い、あとお金との相談とい うのもあったんですが(笑)。家からは琵琶湖の他に、三上山も見えますし、景色、風土がとても気に入っています。歴史の厚みもものすごくある。おそらくそ れが土壌になっているのでしょうが、生活自体がゆったりしている、おちつきがあるというのか、せかせかしていない感覚は非常に好きですね。ものを考える環 境としては、とてもよいと思います。妻は伊豆の出身なので、ちょっと冬の寒さに対して不満なようなんですが(笑)。湖西線も強風でよく止まるし。まぁ、そ れを差し引いても、近江は好きですね。
先ほど言い落としたことをつけ加えると、「近江学」はいろいろな分野で近江を対象として深めていくということなんですが、私の担当としては、「近江 人」、出て行った人もやってきた人も含めてですが、「彼らの営みの記録係」、この土壌で展開されてきたいろいろな営みを整理しながら記録して、未来に提供 する、そういう役割を担えたらと思っています。
▽本日はお忙しいところ、長時間のお話をお聞かせいただきありがとうございました。今後のご研究も楽しみにしております。
(2009年2月3日、水本研究室にて)
●エピローグ
水本先生の著書2冊を読んでいた私は、『近江学』創刊号にも寄稿なさっていることがわかると、その宣伝にかこつけて、インタビューをお願いした。
終了後の会話にて。「一種の〝異文化論〟として農村の歴史はこれからも注目されるでしょう。そこで気になるのは、一面的に過去をもてはやす傾向があるこ とです。臭い肥タゴはいやだから、それを克服するものとして化学肥料ができたんであって、その営み自体を無効にしてはいけない」
至言だと思うから、ここで書いておく。(キ)
ページ: 1 2


 サンライズ出版
サンライズ出版