2009年 4月 1日
其の二十一 優美な紋様をもつ流雲紋瓦(りゅううんもんがわら)

大津宮に深く関わりをもつ寺院としてよく知られている南滋賀町廃寺(大津市南志賀)から、サソリ紋瓦(方形軒先瓦)とともに、もう一種類、特異な紋様(優美といった方がよいかもしれませんが…)の瓦が見つかっています。「流雲紋(飛雲紋ともいいます)軒丸瓦」という名前で呼ばれているこの瓦は、いわゆる屋根の軒先を飾る丸い瓦の周縁部に流れる雲のような紋様が八個、時計回り(反時計回りの例もあります)にあしらわれていることから、この名前が付けられました。軒丸瓦とセットになる軒平瓦にも同じ紋様が表現されており、建物の軒先に葺かれた様子は優美な印象を与えるのではないでしょうか。
この流雲紋の瓦は、近江国府跡(大津市三大寺・大江ほか)や、周辺部にある国府関連遺跡(堂ノ上遺跡、惣山遺跡、瀬田廃寺など)から数多く発見されています。流雲紋の形や方向、中央に配された蓮華紋の形などから数種に分かれますが、基本的には周縁部に流雲紋を表現する点で変りありません。
しかし、この瓦は特異な分布を示しており、近江国府や周辺の国府関連遺跡、南滋賀町廃寺のほか、県内では、日置前廃寺(高島郡今津町)と東浅井郡湖北町今西から見つかっているだけです。県外でも、平城京跡・長岡京跡・平安京跡、下野国分寺跡などあまり多くありません。しかも、そのいずれもが軒平瓦のみで、軒丸瓦に流雲紋をもつ例は大津市域以外では、先の湖北町今西出土の一例が報告されているだけです。
紋様もさることながら、その分布にも特異な点をもつこの瓦は、奈良時代から平安時代にかけての近江の歴史を知る貴重な資料であることから、早急に、その特異性を解明していく必要があります。




 西河原森ノ内遺跡は、野洲郡中主町西河原に所在する遺跡で、大きく三つの遺構面がある。このうち下層では七世紀後半から八世紀前半の掘立柱建物群が検出され、規模も大きく柱の掘り方も一辺一・五メートルのものも見られる。そしてそこからは、多数の木簡や墨書土器、さらに木製の矛・斉串・人形・馬形・陽物・舟形・琴柱・鞍など祭りに関る遺物が出土し、普通の村というより地方の役所のような施設である可能性が高い。この遺跡では合計四点の木簡が出土しており、いずれも注目すべき内容を持っているが、このうち森ノ内二号木簡は、衣知評という記載から七世紀後半のものとみられる文書木簡であるが、その内容は、近江国庁か中央政府の官人とみられる「椋直」(内蔵直)なるものが西河原森ノ内遺跡(馬道郷)に居住する卜部(某)に対し、自ら取りに行ったところ、運搬に使う馬が得られなかったので運ぶことができなかった。そこでおまえが代わりに舟人を率いて行ってくれ、その稲の在る所は衣知評平留五十戸の旦波博士の家であるとするもので、琵琶湖の水運を利用した物資の運搬がなされていたことを示している。他の木簡や墨書土器から、西河原森ノ内遺跡には志賀漢人と総称される倭漢氏配下の渡来氏族の顕著な居住が知られ、しかも旦波博士も志賀漢人一族の大友丹波史であり、湖上水運を利用した物資の運搬に、倭漢氏の一族である内蔵直氏と、その配下である漢人村主の志賀漢人一族の関与が知られることは注目される。
西河原森ノ内遺跡は、野洲郡中主町西河原に所在する遺跡で、大きく三つの遺構面がある。このうち下層では七世紀後半から八世紀前半の掘立柱建物群が検出され、規模も大きく柱の掘り方も一辺一・五メートルのものも見られる。そしてそこからは、多数の木簡や墨書土器、さらに木製の矛・斉串・人形・馬形・陽物・舟形・琴柱・鞍など祭りに関る遺物が出土し、普通の村というより地方の役所のような施設である可能性が高い。この遺跡では合計四点の木簡が出土しており、いずれも注目すべき内容を持っているが、このうち森ノ内二号木簡は、衣知評という記載から七世紀後半のものとみられる文書木簡であるが、その内容は、近江国庁か中央政府の官人とみられる「椋直」(内蔵直)なるものが西河原森ノ内遺跡(馬道郷)に居住する卜部(某)に対し、自ら取りに行ったところ、運搬に使う馬が得られなかったので運ぶことができなかった。そこでおまえが代わりに舟人を率いて行ってくれ、その稲の在る所は衣知評平留五十戸の旦波博士の家であるとするもので、琵琶湖の水運を利用した物資の運搬がなされていたことを示している。他の木簡や墨書土器から、西河原森ノ内遺跡には志賀漢人と総称される倭漢氏配下の渡来氏族の顕著な居住が知られ、しかも旦波博士も志賀漢人一族の大友丹波史であり、湖上水運を利用した物資の運搬に、倭漢氏の一族である内蔵直氏と、その配下である漢人村主の志賀漢人一族の関与が知られることは注目される。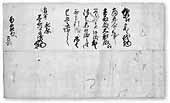





 サンライズ出版
サンライズ出版